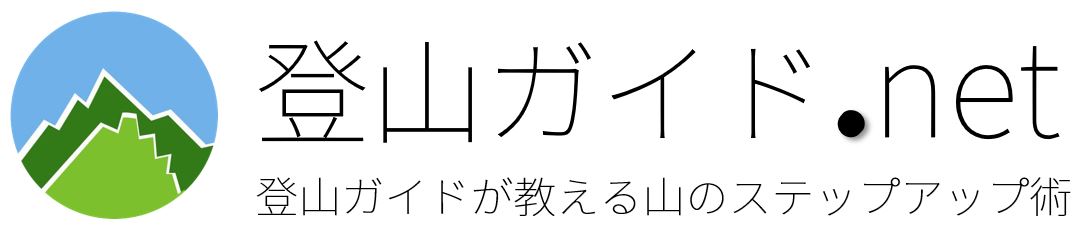当ページでは、登山ツアーや講習会などで受けたお客様からの質問の回答を中心に、登山技術やオススメの山などを掲載してまいります。
コロナ渦でのガイド登山再開~withコロナで登山ツアーは何が変わったか
2020年に世界規模で猛威を振るった新型コロナウイルス(COVID-19)。日本では4月から非常事態宣言を行い、ステイホーム・外出自粛が始まり、およそ1ケ月後に解除されました。
妙義山 星穴岳~奇妙な山容とわかりづらいルートで空中懸垂。バリエーションルート2
妙義山系星穴岳。ロープワークを学んできた人にとっては一つの「ご褒美」ともいえる空中懸垂のフィナーレを味わえる山はそうありません。
これって高山病?~高山病の簡単な判定方法~富士山など3000m超の山に登る人に知ってほしい事
頭痛、吐き気、食欲不振、不眠などが顕著な症状です。高山病は、軽度なうちに高度を下げれば何事もなかったように回復するのが特長でもあります。AMS判定表を用いて急性高山病の判定法とその対策を紹介します。
様々な懸垂下降~ATC、エイト環+バックアップ
懸垂下降には数々の方法があります。技術を教わる組織・団体によりその方法は様々です。最も良い方法は、クライマー本人が幾度も練習を重ね、何の迷いもなく安全な手順を繰り返すことができる方法です。登山ガイド.netで標準的な方法として指導している懸垂下降の方法と 私がこれまで見てきた方法のいくつかを以下にご紹介します。
【字幕動画】マルチピッチでの最終支点構築とセカンドビレイ手順(ロープワーク)
PAS、カラビナ、スリング、ATC( ルベルソ)を用いた、基本的な支点構築とセカンドビレイセットまでの流れを字幕入り動画にまとめました。
富士山は高尾山に比較して6倍難しい?~いいえ、富士登山を高尾山とデータで徹底比較
富士登山。日本一の標高を誇る富士山に一度は登ってみたい。そう考える方も多くいらっしゃると思います。その富士山に「私にも登れるだろうか?」これまでのガイド経験の中で多くの質問を受けてきたのが富士山の難易度。
この質問、良くいただきます。
今回は富士山の難易度・困難さを、関東で最もポピュラーな山の一つ、高尾山と比較してみました。
一度でも高尾山に登ったことのある方や、これから高尾山に登る計画のある方に役に立つ記事にしようと思います。
バリエーションルート入門~ジャンダルム登頂への戦略
「国内一般登山道における最難関」「バリエーションルートの入門編」「ロープ無しで登れる最後の課題」
様々な形容がされる西穂高~奥穂高縦走。その途中にはだかる難関峰、ジャンダルムが立ちはだかる。
多くの山やルートを踏破されてきた登山上級者の方がジャンダルムを目指すにあたり、必要とされる登山技術に限らない成功確率を高める戦略・ストラテジーをまとめてみたいと思います。
冬山でのビバーク術(冬山で下山不能に。日帰り装備で翌朝を迎える装備と方法)
日帰り装備で ビバークをする方法を紹介します。ビバークの勝利条件は「翌朝まで持ちこたえること」
不測の事態に備え、たとえ日帰りであったとしても、冬山山行における装備を今一度見直してみるのはいかがでしょうか。
【字幕動画】ATCでの懸垂下降手順 (ロープワーク)
様々なやり方がある懸垂下降。皆さんはどんなやり方を用いてますか?多くの山岳会やガイドを用いる最新かつ標準的な懸垂下降の方法を字幕付き1分動画でお見せします。
雨の日の登山対策(登山中に雨が降ってきた時の対策と実践)
雨の日の登山を避け続けていては、登山技術が高まらない。自分にとってチャレンジングな登山をする前に、雨の日登山をシミュレーションしておきましょう。