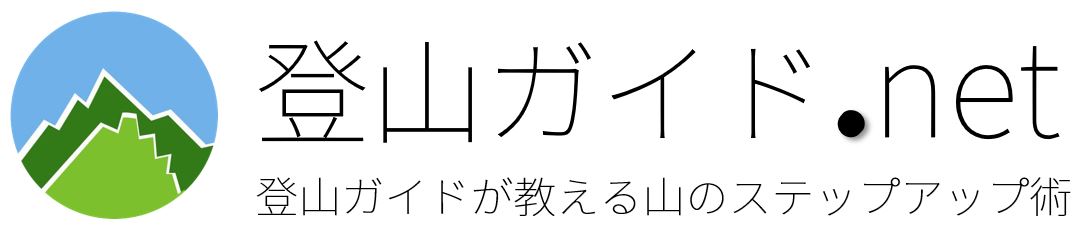富士山は高尾山に比較して6倍難しい?~いいえ、富士登山を高尾山とデータで徹底比較
富士登山。日本一の標高を誇る富士山に一度は登ってみたい。そう考える方も多くいらっしゃると思います。その富士山に「私にも登れるだろうか?」
この質問、良くいただきます。
これまでのガイド経験の中で多くの質問を受けてきたのが富士山の難易度。
今回は富士山の難易度・困難さを、関東で最もポピュラーな山の一つ、高尾山と比較してみました。
一度でも高尾山に登ったことのある方や、これから高尾山に登る計画のある方に役に立つ記事にしようと思います。

富士山と高尾山のスペック比較
3,776mの富士山と599mの高尾山。標高でいえば6倍の差。では富士山は高尾山の6倍難しいのか?
いいえ。そんなことはありません。高尾山の方が断然簡単ですが、富士山の6倍も難しいことはありません。ではどれ程難しいのでしょうか?
ここでは、多面的に比較をしていこうと思います。
・地図の比較
・標高差
・距離
・標準 コースタイム
・技術的難易度
・想定されるリスクと遭難原因
・必要装備と対策
比較上の前提条件
当記事では二つの山を比較する上で、下記を前提条件とします。
どちらも登山ツアーでは一般的な条件となります。
記事中の数値データは実際の登山ツアーで集計した物を使用します。
◆高尾山
登山口:京王線高尾山口駅
登り:稲荷山コース
登頂点:高尾山頂(大見晴台)
下り:薬王院経由1号路
下山口: 京王線高尾山口駅
時期:秋期~春期
◆富士山
登山口:富士スバルライン五合目
登り: 富士吉田コース(吉田口登山道)
登頂点:久須志神社
下り: 富士吉田コース(吉田口下山道)
下山口:富士スバルライン五合目
※八合目の山小屋で1泊
時期:夏期
少々長くなることと思いますが最後までお付き合い願います!
地図の比較


紫色で引かれた線がそれぞれの山の登山コースです。こうみるとそれほど距離に差は無いように見えますね。
しかしこの線には裏があります。高低差が表現されていないのです。
地図上の紫線は平面距離であり、高低差を勘案した「沿面距離」の差は更に大きくなります。
その差についてもこの後詳しく説明します。
山の記録を共有できるサイト ヤマレコ内の新機能「ヤマプラ」は昭文社の「山と高原地図」を閲覧することができ、更にコースタイム付きプランを簡単にできる便利サイトです。ヤマプラでは出発点・到着点・ルートを指定することにより、地図の右側に標準コースタイムと距離が表示されます。これらデータを引き続き比較してまいります。
標高差
国土地理院のGSI Mapsはとても有用です。ツール – 断面図 機能で登るルート、登ったルートの断面を図で見ることができる。このサイトを使えば登山時に記録したGPSデータ(KLMデータ)をアップロードすることで登ったルートの距離や高低差をグラフ化することができます。

上記が高尾山のルートの断面図。全体の距離に対し高低差がこれだけ。のっぺりとした印象が。

一方、上記は富士山のルートの断面図。富士山を遠目に見た形に近いものがあります。
ただ、上記2つの図は縦横の縮尺が異なります。GSI Mapsでは全体の距離を一定の横軸にします。そのため、ここでは縦横比を補正します。富士山と高尾山の断面図を重ね合わせてみると・・・。

加工:登山ガイド.net
富士山の標高差と距離を比較するとどれ程か。ビジュアル的に比較するとこのようになります。累積標高差は3倍程、距離では2倍ほどになります。
次に数値で比較をしてみます。

◆登山口の標高が圧倒的に高い
・富士山登山口の標高は高尾山登山口の11倍
◆山頂の標高は6倍
◆標高差(単純)は3.5倍
◆累積標高差は2.9倍
以上の違いが2つの山に存在します。
累積標高差の比較では2.9倍の差が。高尾山を1単位として比較すれば、富士山の標高差は「2.9高尾山」です。
距離
では距離ではどうでしょう。

距離でいえば2倍の開き。標高差の2.9と比べれば距離差は小さく、高尾山の方がなだらか、富士山の方が急な登山道と言えます。
富士山の距離は「2.0高尾山」です。
標準コースタイム
コースタイム(CT)比較です。

上記の「実際コースタイム」は
・ツアーのお客様二十数名全員が脱落することなく全員が頂上まで到達でき、全員無事下山できる程度のコースタイムです。
・休憩時間を含みます。
・富士山ツアーは1泊2日の為、行動中の休憩時間を含みますが、8合目の山小屋到着後から出発時間までの時間は加算していません。
比較表を見ると実際コースタイム実績に大きな差が出ています。これは
・頂上での大休止時間
・折り返しや頂上直下の登山渋滞
・高山帯でのこまめな休憩
等の影響です。
難易度
富士山と高尾山における客観的な難易度の比較。なかなか難しい比較となります。
ここでは 登山ルートグレーディング表を用いて比較をします。

上記表では富士山(スバルライン五合目)は技術的難易度ではB、体力度で5との表記があります。
一方高尾山は別のグレーディング表にて技術的難易度でA、体力度で2との表記があります。
5段階の技術的難易度で、富士山:高尾山では2:1
10段階の体力度で、富士山:高尾山では5:2
グレーディング表の性質上、単純に比較はできませんが、技術的難易度・体力度共に富士山の方が上回っていることは間違いありません。また、高尾山と比較すれば富士山は技術度以上に体力度を求められるともいえます。
空気(酸素)の薄さ比較
空気中に含まれる酸素量を比較すると

海面(海抜0m)に比較して富士山は空気が薄く、酸素量も36%少ないことがわかります。
空気が薄ければ行動時間が長引くほど体に負担がかかります。登山者が本来持ちうるパフォーマンスも十分に引き出せずに消耗、ペースダウンが考えられます。
また標高が高い富士山は行動時間中の天候・気温・風速も変動が大きいことが多く、その対策も困難なものとなります。
これまでの比較のまとめ
富士山と高尾山のこれまでの比較をまとめてみます。

富士山は高尾山と比べ・・・
・山頂は 6倍高く
・累積標高差は 約3倍
・距離は 2倍
・コースタイムは 約4倍
・空気・酸素は 3割薄い
更には
・技術的にも5段階中1段階難しく
・体力度でいえば10段階中3段階厳しい
数字上ではこのような比較となります。
次回予告
今回は初めて富士山に登る方を対象に、富士山を身近な高尾山に比較してみました。
富士山と高尾山の比較特集、次回は上記の比較からの考察(インサイト)を紹介したいと思います。
起こりうる困難、リスク、必要な装備や対策など、より富士登山の成功確率を高まるアドバイスも。

旅行会社主催の登山ツアーで講師(ガイド)を務める「登山ガイド.net」管理人の 矢ケ崎 晶 です。
一年間に千人超のお客様と登山を楽しんでいます。その際、登山中に受けたご質問を中心に当サイトに記録して参ります。
これからも優しい丁寧なガイドを目指し究めます!